小さい子を保育園に預けると、実にいろんな病気にかかります。
特に0歳・1歳での入園では、入園した初月から病気との戦いになります。慣らし保育が終わって、いざ復職となった初日に、子が発熱して復職出来ず、なんてことも珍しくありません。
子どもが病気した時に利用できる施設として「病後児保育室」があります。
我が家も定期的に利用していました。トータル10回以上は利用したでしょうか。きょうだい同時に預けたこともあります。
以下、私が利用していた病後児保育室の例で説明しています。自治体によって利用方法や利用できる条件が違うので、詳しくは自治体に問合せしてください。
・病後児保育室とは?
・具体的な利用方法と感想。
病児保育と病後児保育の違いとは?
ややこしいのですが、病気の子を預かる施設には病児保育と、病後児保育があり、私が利用していたのは病後児保育の方です。
病後児保育は回復期の子を預かる場所。
【病児保育】
その名の通り、病気中でも預かって貰えます。医院やクリニック等、医療機関が運営しているため、数が少ないです。病気中でも預かって貰えますが、重篤な場合はもちろん預けられません。高熱でも元気な時に利用するイメージだと思います。
【病後児保育】
あくまで病後児であって、病児ではないことがポイントです。病気の山は越えたけど、まだ本調子じゃない時に利用する施設になります。回復期の子を預かる、と説明には書かれていました。
病後児保育の特徴とは?
少し高めの熱でも預かりOKで、かつ、投薬をしてくれます。通常の保育園は投薬してくれません(看護師が常駐している園でも、投薬に厳しい園が多いです)。
医療機関が運営している施設と、保育園が運営している施設があります。私が利用していたところは、保育園が運営しており、看護師と保育士両方の資格を持った先生がいました。病後児保育室に予約が入らない場合は通常園のヘルプ保育士として働かれています。
※すべての自治体に病児保育、病後児保育はありません。自治体によって利用できる年齢や金額、時間が違います。
病後児保育の利用までの手続きと注意点。
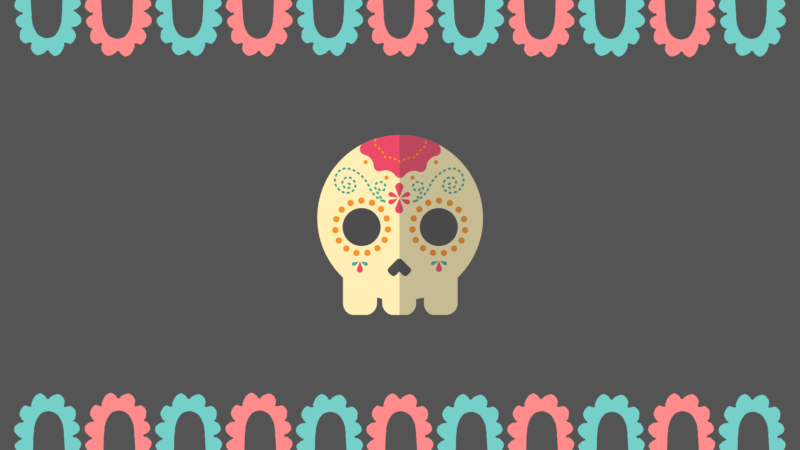
「病後児保育室」なんてものがあるんだ。へ~。便利な世の中だなぁ。
と思ったら大間違いであり、利用するにはそれなりに手続きを踏まないといけません。
働くママやパパが
「病後児に預けた」
と言っていたら、それはある程度の覚悟と気合があってのことだ、と思って欲しいところです。
一筋縄じゃ利用できないのですから!!
説明会に参加して事前登録を済ませる。
病後児保育室は、子どもが病気になってから慌てて登録というのは出来ません。事前に説明会に参加して、登録を済ませておく必要があります。
私が利用していたところは、保育施設、小学校に在籍している子が対象でしたので、保育園の決定通知書が来てから育児休業中に登録しました。
※自治体によっては家庭保育の子(未就園児)でも利用可能なところもあります。
2人目の場合、説明会は飛ばして、書類提出だけで済みました。
↑こういう部分、融通が効く自治体で良かったです。
利用するには医師の診察と書類が必要。
利用したいとなった時、医療機関で医師の診察を受け「情報提供書」を書いてもらいます。これが無いと利用できません。
さて、ここで一つの問題が。
保育園激戦区や、激戦とまでいかなくても人口の多い場所に住んでいると、自治体が運営している子ども用施設は予約が殺到します。小児科が常に混んでいるような地域=子どもに関連する施設も混む、と思った方がいいです。
病後児保育室も、病気が流行るシーズンは予約合戦になります。だから、戦略的に動かないと利用できません。
早めに確保しないと病後児保育室の枠が埋まってしまいます。でも医療機関で書類を書いてもらわないと利用が出来ない。小児科を受診するのもなかなかの手間なのに、予約をしたいがためにすぐに小児科にかからなければなりません。これがなかなかのジレンマです。
また、例えば土曜日の夜に発熱したパターンだと、月曜日に利用したくても、日曜日は小児科は休みで、病後児保育室も休みなので予約の電話すらかけられないことになります。
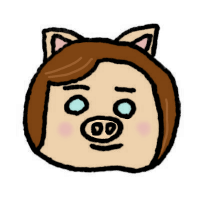
ぐぬぬぬ。
利用するまでハードル高い。
同じ症状の子しか預かってくれない。
私が利用していた病後児保育室は1日3名までで、しかも先に予約していた子と病状が同じ場合のみ、という利用ルールがありました。手足口病の子が先に予約をしていると、胃腸炎の子は予約できないといった具合です。
たとえ予約人数に余裕があっても、病気の種類や予約順序によって預かってもらえないパターンがあるのです。
すなわち、病後児保育室は予約できるか否かはその時の運によるところが大きいのです。
また、インフルエンザ、麻疹や流行性角結膜炎の場合は利用できません。
【病後児保育室利用までの注意点】
・事前に登録しておく必要がある。
・医療機関を受診し、書類を書いてもらう必要がある。
・予約枠に余裕があっても予約できない場合がある。
病後児保育室、利用までの具体的な手順。
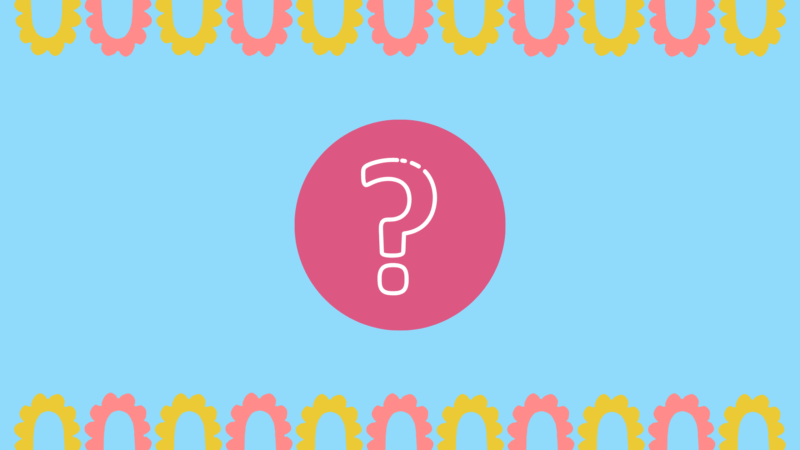
ここまでお読み頂き、利用するまでのハードル高すぎ!!と思ったあなた。大丈夫です。
説明会ではいろいろ言われますが、慣れてくるとサクッと利用できるようになります。私は医師の診察を受ける前に仮予約をしていました。手元に医師による書類が無くてもとにかく予約するのです。
とりあえず予約する。
0歳や1歳の子は、2~3日は熱が下がりません。だから翌日と翌々日の予約は諦め、その日の3日後の予約を入れます。月曜日に発熱したとすると、木曜日と金曜日に予約を入れます。キャンセルは当日の9時まで受け付けてくれるので、利用するか否かは後で考え、まずは予約をするのです。
説明会では「医師の診察が必要。医療機関で書類を書いてもらってから予約になる」と言われたのですが、これはあくまでも原則です。
ある時、病後児保育室の先生に相談しました。
「まだ医療機関受診していないけど、予約できませんか?」と。すると先生が「仮で押さえておくから、とりあず書類とって来て。でも今日中に書類貰えなければ他の人の予約を優先するからね!」と言われました。原則から外れる行為ですが、何度も利用しているうちに融通が効くようになりました。
ワーママしていると分かってくるのですが、何事もテクニックがあります。私も上記の方法は先輩ママに聞いて実行しました。
利用規約にはこう書かれているからと、真面目にやっていちゃいかん。先生に相談しろ!!
と言われまして。確かに言うのはタダだわ、と思って聞いてみたらいけました。
小児科を受診する。
予約をしたら、次は小児科を受診し、書類を書いてもらいます。
もし病後児保育が利用できない感染症と判明した場合は、すぐに病後児保育室をキャンセルします。
前述の通り、病気発覚の3日後、4日後に予約を取っているので、それよりも早くに回復した場合や、予約日に充分熱が下がっていなかった場合、当日の朝にキャンセルをしていました。
キャンセルはいつでもできるのだから、さっさと予約するのが吉です。
書類と持ち物を整える。
書類はたくさん必要ですが、持ち物は通常園とあまり変わりません。通常園のバッグに書類を入れて持って行きました。
書類
・情報提供書(医師が記入)。
・利用申込書(保護者が記入)。
・投薬指示書(保護者が記入)。
・連絡票(子の様子を書いた紙。通常園の連絡帳と同じ)。
持ち物
・母子手帳。
・着替え、オムツ。
・お食事エプロン。
・お尻ふき。
・1日分の利用料。
等。
病後児保育室の利用料他。
利用料や預かり時間は自治体や、施設によってかなりばらつきがあります。お昼やおやつが持ち込みのところと、提供されるところとあります。
私が利用していた施設の場合。
利用料:3,000円/日
利用時間:9時~17時
給食:あり
おやつ:あり
中には無料で利用できる自治体もあるようです。羨ましい限り。
病後児保育室はお迎え時間がシビア。
お迎え時間は通常園よりシビアでした。1分でも遅れることが許されません。
当時は8時半~16時半の勤務時間で、通勤時間が片道20分程度でしたので、朝は遅刻になりますし、帰りは定時ピッタリに退勤しても、電車遅延すると間に合わないので、5分だけ早退していました。
利用時間が通常より短めに設定されているので仕方がないです。
病後児保育室の感想とまとめ。
病後児保育を利用してみての感想。
通算10回以上利用しました。2人まとめて預かって貰ったこともあります。社外の方との打ち合わせで、スケジュールの再設定が難しい場合などはとても助かりました。
しかし子どもが病気の時は、無理せず休んだ方がいいと思います。
予約、受診、準備、と利用までが手間ですし、いつもと違う保育園だと勝手が違い、親子ともに疲れてしまうからです。
どうしても仕方ない時の奥の手、くらいに思って利用するのがいいです。
子どもが大きくなった今は利用する機会もなくなりました。
誰かの参考になれば幸いです。
最後に愚痴。
行政サービスが自治体ごとによってまちまちなの、どうにかならないのでしょうか。この記事にも何度も書いていますが、自治体によって内容が違い過ぎます。
せめてどの自治体にも、何かしらのサービスが存在していて欲しいです。まったく無いというのは困りものです。

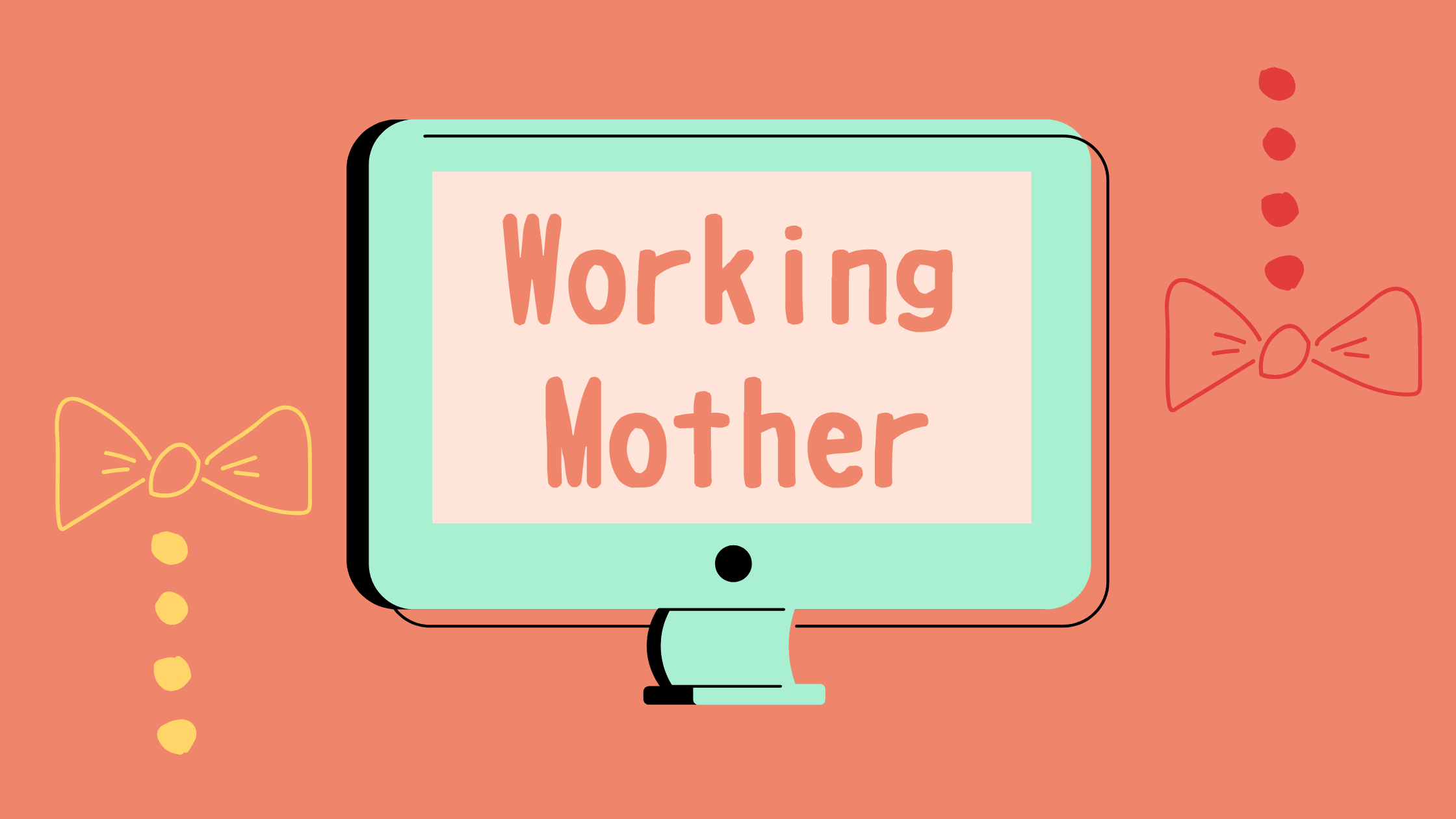


コメント